「注文住宅の予算って、どうやって決めればいいの?」
家づくりを考え始めると、まず気になるのが「予算」の問題ですよね。
「こだわりたい部分はたくさんあるけど、どこまでお金をかけていいのかわからない…」
そんな悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
実は、住宅の予算をしっかり決めることで、無理なく理想の家を手に入れることができます!
逆に、予算をあいまいにしたまま進めてしまうと、後から「こんなはずじゃなかった…」と後悔することも…
今回の記事では
- 予算の基本構成と決め方のステップ
- 無理のない住宅ローンの考え方
- コストを抑えながら理想の家を実現するコツ
といった、失敗しない住宅予算の決め方を詳しく解説していきます。
「家づくりはお金の計画から」
しっかりと準備をして、安心して理想の住まいを実現しましょう!
1.住宅の予算を決める重要性

家を建てると決めたら、まず考えるべきなのが「予算」です。
注文住宅を建てる際、「どんな家を建てるか」だけでなく、「いくらかけられるのか」を明確にすることが重要になってきます。予算をしっかり決めないと、後で資金不足に陥ったり、住宅ローンの返済が苦しくなることも…
無理のない計画を立てることが、後悔しない家づくりの第一歩です。
予算を決めずに家づくりを始めてしまうと…
予算を決めずに家づくりを始めてしまうと、予想外の後悔や失敗につながってしまう可能性が上がります。
- 希望の間取り・設備を詰め込んだ結果、予算オーバー
→途中で妥協が必要になる - 住宅ローンの借入額を増やしてしまう
→返済が苦しくなる - 諸費用や外構費を見落とす
→予想以上の出費が発生

我が家でも最初はざっくり、いくらまでにという予算を決めるところから進めましたが、理想と現実は違い、叶えたいことを組み込んでいくことで当初設定していた予算以上の金額になってしまいました…
理想(叶えたいこと)と現実(リアルに出せるお金)とのバランスを考えることになりますが、最初に予算を決めておくことで、これ以上は…と踏みとどまることができますので、無理のない資金計画のためにもまずは予算を考えましょう!
2.住宅予算の基本構成

住宅の予算は、大きく分けて以下の要素で構成されます。
| 項目 | 内容 | 目安の割合(参考) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土地費用 | 土地代、仲介手数料、登記費用、地盤調査など | 約30~40%(土地購入がある場合) | 建て替えの場合は不要 解体・整地費が出ることも |
| 建物本体工事費 | 建物の本体価格、設計料 | 約40~50% | 坪単価だけで判断せず、標準仕様の内容を確認 |
| 付帯工事費・外構費 | 駐車場、フェンス、地盤改良、上下水道引込など | 約10~15% | 後回しにせず、新築時に予算化を |
| 諸費用 | 登記費、保険、印紙税、引っ越し費用など | 約5~10% | 契約関連や手続きにかかる費用で地味に高額 |
| 住宅ローン関連費 | 手数料、保証料、団信、抵当権設定など | 約2~5% | 金融機関によって差あり ローン諸費用込のケースも |
| 家具・家電・カーテン等 | 新生活に必要な家具や家電、窓周り用品など | 約5~10% | 初めての新築では出費がかさむので要注意 |
建築費用だけでなく、これらすべてを含めた総予算を考えることが大切です。
これから、住宅予算の基本構成について一つずつ解説していきます。
2-1. 土地費用(建て替えの場合は除く)
家を建てるには、まず土地が必要です。
土地費用とは、家を建てるための土地にかかる費用全般を指します。
土地そのものの価格のほか、登記費用や仲介手数料も含みます。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 土地代 | 土地の購入価格 |
| 仲介手数料 | 不動産会社への手数料(最大で物件価格の3%+6万円) |
| 登記費用 | 所有権移転登記などの費用 |
| 土地整備費 | 解体・地盤調査・地盤改良などが必要な場合も |
2-2. 建物本体工事費
建物本体工事費とは、住宅そのものを建てるための基本的な工事費です。
建物の構造や間取り、断熱・耐震性能などに関わる最も大きな費用項目です。
住宅メーカーの広告などでよく見る「坪単価」はこの部分にあたります。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 建物価格 | 本体構造・仕様・間取りによって変動 |
| 設計料 | 設計事務所やハウスメーカーに支払う設計費 |
2-3. 付帯工事費・外構費
付帯工事費・外構費とは、本体以外にかかる、「家のまわりを整える工事」の費用です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外構工事 | 駐車場・フェンス・庭・門柱など |
| インフラ整備 | 電気・水道・ガスの引き込み |
| 地盤改良 | 軟弱地盤に必要な補強工事 |
| 解体工事 | 建て替えの場合必要になる既存建物の解体費 |

我が家でも外構は最後だったので、予算が後回しになり正直想定よりもお金をかけれなかったです…「外構にはいくらかける」と最初の段階でしっかり計画をしておくことが大事だと思います!
2-4. 諸費用(手続き・税金・保険など)
家づくりにおける諸費用とは、家づくりにかかるさまざまな手続きや税金、保険の費用です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登記費用 | 建物の所有権登記・表示登記・保存登記など |
| 各種保険料(火災保険・地震保険) | 必須の保険費用(5年分まとめて支払いなど) |
| 印紙税 | 契約書に必要な税金 |
| 引っ越し費用 | 仮住まい・荷物の移動などにかかる費用 |
2-5. 住宅ローン関連費
住宅ローン関連費とは、ローンを組む際に必要な各種費用のことです。
借入時の諸経費や保証料などが含まれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事務手数料 | 金融機関に支払う融資手続きの費用 |
| 保証料or保手数料手数料 | ローン返済の保証に関わる費用 |
| 団体信用生命保険 | 万が一に備える生命保険 |
| 金融機関との手続き費用 | 抵当権設定登記費用や印紙税など |
2-6. 家具・家電・カーテンなどの生活費用
家具・家電・カーテンなどの生活費用とは、実際の生活を始めるために必要な家具やカーテンなどのアイテム購入費です。
家具や家電、照明、カーテンなども見落とされがちですが、事前にしっかり見積もりを準備しておきましょう。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 家具 | ベッド・ダイニングセット・収納・家具など |
| 家電 | 冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビなど |
| 窓周り | カーテン・ブラインド・ロールスクリーンなど |
2-7. 住宅予算の構成 まとめ
住宅の予算は建物代だけの把握では不十分です。
予算の全体構成を把握し、土地・工事・手続き・家具・そしてローンにかかる費用まで、全てを含めた総予算を立てることが、失敗しない家づくりの第一歩です。
3.予算の決め方のステップ

3-1. 家づくりにかけられる総額を決める
まず、自己資金(貯金)+借入可能額(住宅ローン)=家づくりの総予算という考え方を基本にしましょう。
一般的に「年収の5倍~7倍」が住宅ローンの借入上限とされがちですが、このような基準は気にせず、毎月の支払いが家計を圧迫しない範囲で設定することが重要です。
住宅ローンの返済負担率(年収に対する年間ローン返済額の割合)は20%~25%以内が安心。
→例えば、年収500万円なら、年間返済額100~125万円(月8.3~10.4万円)以内が理想
3-2. 優先順位を決める(こだわる部分・コストダウンする部分)
理想の家を考えると、どんどん「これも欲しい!」と予算が膨らみがちです。
実際、我が家もそうなりました…
メリハリをつけるため、以下のように優先順位を決めると予算オーバーを防げます。
| 優先度 | 具体例 |
|---|---|
| ★★★ こだわりたい(お金をかける) | 断熱性能・耐震性・キッチン設備・間取り |
| ★★ 標準レベルでOK | 外壁・床材・収納 |
| ★ コストダウンできるかも? | 照明・壁紙・設備のグレード |
優先順位を決めるポイント
- ライフスタイルに直結するものを最優先
例.広いリビングが欲しい/収納を充実させたい/高断熱仕様にしたい - デザインや仕様は柔軟に考える
例.キッチンのグレード/床材の種類/外壁の素材 - 後から変更できるものは後回しに
例.エアコン/照明/カーテン

誰もが、できるなら理想を全て叶えたいと思いますが、実態として全ては難しいと思いますので、「これは絶対譲れない」というものから優先順位を決めて予算を配分していくと良いと思います。
我が家でも、そこまでこだわりがない部分は標準か、それ以下に落としたものもあります。
3-3. 将来の支出も考慮する

1. 長期的なライフプランを考える
住宅の購入は長期的なライフプランの一部です。
今の家計状況も、もちろん大事ですが、住宅ローンは何十年と長期間で返済していくことが一般的ですので、将来的に想定される支出も考慮して予算組みすることが重要になります。
例えば、
- 教育費
→子どもの進学費用 - 老後資金
→退職後も返済が続かないか? - ライフスタイルの変化
→転職・介護・趣味の費用など
順番に解説していきます。
①教育費→子どもの進学費用は?
お子さんがいる家庭は、教育費が大きな支出の一つになります。
特に大学進学となると、年間100万以上の学費が必要になることも…
住宅ローンを組む際は、子どもが進学するタイミングの家計の負担も考慮する必要があります。
▼進学費用の目安
| 教育段階 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年間) | 約70万円 | 約150万円 |
| 小学校(6年間) | 約200万円 | 約900万円 |
| 中学校(3年間) | 約150万円 | 約420万円 |
| 高校(3年間) | 約135万円 | 約290万円 |
| 大学(4年間) | 約500万円 | 約800万円(理系は+200万円) |

我が家には子どもが2人いますので、将来の教育費をまかなえるように、毎月定額をNISAにて投資しています。
教育は将来のライフプランにおける出費が大きい部分ですので、想定しておきたいポイントです!
②老後資金→退職後も返済が続かないか?
住宅ローンを組む際、老後資金の確保も重要なポイントです。
例えば、35歳で35年ローンを組むと、完済時には70歳…
退職後もローンが残る場合、年金収入だけで生活できるかを考える必要があります。
▼老後資金の目安
老後の生活費は、(もちろん各家庭によって異なりますが)一般的には夫婦2人で月22万~30万程度と言われています。
仮に30年間生きるとすると、必要な老後資金は約8,000万にもなります。
| 項目 | 夫婦の目安額(30年間) |
|---|---|
| 生活費 | 約8,000万円 |
| 医療費 | 約1,000万円 |
| 介護費 | 約500万円 |
| 旅行・趣味 | 約500万円 |

我が家も老後を考慮した資金計画を立ててローン年数を決めました。
詳細に関してはまた別の記事にて紹介したいと思います。
③ライフスタイルの変化→転職・介護・趣味の費用など
人生は計画通りに進まないことが多いです。
住宅ローンを組んだ後、以下のようなライフイベントが発生する可能性を考慮しましょう。
▼主なライフイベントとその影響
| ライフイベント | 影響する支出 | 備考 |
|---|---|---|
| 転職・収入減 | 住宅ローン返済に影響 | 返済計画を柔軟に考える |
| 親の介護 | 施設費・医療費の増額 | 在宅介護ならリフォーム費用も検討 |
| 子どもの独立 | 生活費の変動 | 夫婦2人の生活を想定した住まいも検討 |
| 趣味・旅行 | 余暇の支出増 | ローン返済だけで生活が圧迫されないように |
2.将来的な住宅の維持費を把握する
家を建てた後も、住宅にはさまざまな維持費用がかかります。
短期的な支出だけでなく、将来的な費用も考慮して予算を決めましょう。
▼将来の主な支出
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年支払う税金 | 10万~30万円/年 |
| 火災保険・地震保険 | 継続的な保険料 | 10万~50万円/5年 |
| 修繕費 | 設備・外装のメンテナンス | 50万~300万円 |
| 住宅ローンの繰り上げ返済 | 早期返済で総支払い額を軽減 | 100万~500万円 |
▼長期的な修繕費の目安
住宅は10年・20年・30年ごとに大きなメンテナンスが必要になります。
| 築年数 | 修繕内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 10年 | 外壁塗装・シーリング補修 | 50万~150万円 |
| 15~20年 | 屋根の補修・防水工事 | 100万~200万円 |
| 25年~30年 | 給湯器・水回り設備の交換 | 50万~200万円 |
このように、家を建てるときは「今の予算」だけでなく、長期的な支出も考えた上で計画を立てることが重要です。
3. 将来の支出考慮 まとめ
住宅を購入すると、ローン返済だけでなく、教育費・老後資金・ライフイベントへの対応も考慮しなければなりません。
短期的な支出だけでなく、10年後・20年後のライフプランを想定した予算計画を立てることが大切です。
- 教育費はしっかり準備し、進学時の負担を軽減する
- 定年後もローンが残らないよう、早めの完済を目指す
- 将来のライフイベントにも対応できる資金計画を立てる
このように、長期的な視点で住宅購入を計画することが、後悔しない家づくりのポイントです!
4.コストを抑える工夫

4-1. 予算オーバーしやすいポイント
予算を最初の段階で決めていても、予算オーバーになりやすい注意すべきポイントをお伝えします。
大きくは下記3つに注意が必要です。
- オプション追加 → 設備のグレードアップで費用増
- 外構工事の見落とし → 予算不足になりがち
- 家具・家電の買い換え → 想定以上の出費が発生

これに関しては、我が家が完全に当てはまったので知って得する要注意ポイントだと思います!
4-2. コストを抑える具体策
- 優先順位を決める→こだわりたい部分と妥協できる部分を整理
- 相見積もりを取る→ハウスメーカーや工務店で価格が変わるため、比較検討はマスト!
- 補助金を活用する→住宅ローン減税やZEH補助金など活用できる補助金がないかをチェック!
5. 予算を決める際の注意点

最後に、自分も経験した失敗例や想定外だったことなど、予算を決める際に注意しておきたい点について簡単に紹介させていただきます。
こうなることが多いと知っているだけで対策ができると思いますので、「こんなことになるのかぁ」と認識を深め、そうならないように動く参考にしていただければと思います。
5-1. やりがちな失敗例と対策
- ついオプションをつけすぎてしまう→「本当に必要か?」を考える
- 諸費用を見落としていた→住宅ローン以外のコストも事前に把握する
- 予算ギリギリで計画→余裕を持たせた資金計画にする(+100万~200万予備費を確保)
5-2. 想定外の費用が発生するリスク
- 地盤改良が想定より高額に
- 外構費用が後回しになり、最終的に追加費用が発生
- 引っ越し後に家具・家電を買い替えて予算オーバー
5-3. 住宅ローンの選び方の落とし穴
| 金利タイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 固定金利 | 返済額が一定で安心 | 変動金利より金利が高い |
| 変動金利 | 金利が低く、総支払い額が減る可能性 | 将来的に金利が上がるリスク |
6. まとめ
今回は注文住宅購入時に重要となる予算の決め方について、総額の目安、住宅ローンの考え方、コストを抑える工夫の観点から要点を解説させていただきました!
ポイントとしては…
- 住宅予算は本体工事費以外にも多くの費用項目にて構成される
- 住宅ローンは「無理なく返せる金額」で組むことが重要
- 予算には限界があるため、ライフスタイルに直結するものから優先順位をつける
- 予算オーバーしがちなポイントを把握し、コスト管理を徹底する
上記は絶対に抑えておきたい項目です。
住宅購入は「家を建てること」よりも、「無理なく暮らせること」が大切です。
必要な費用をしっかり把握しておくことで、理想の家づくりと安心の暮らしの両方を実現できます!
予算をしっかり準備・管理して予算オーバーしないように、計画的に進めていきましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!





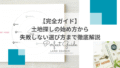
コメント